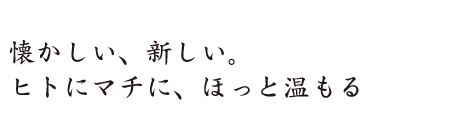ブログを「お手紙紹介」のようにしてしまっていますが…。
以前取材でお世話になった、「増毛山道の会」事務局の方からのメールです。札幌では、初雪の後、雪はもう解けましたが増毛の山中ではもう雪景色なのですね。
江戸時代、増毛〜浜益間にあった山道の復活を目指す「増毛山道の会」では、この山道を造った伊達林右衛門のご子孫や増毛の測量会社の社長さんが中心になり、山道復活を目指しています。測量のハイテク技術によってかつてのルートを探りあて、現在は、山歩きや草刈りといった地道な作業、復活後の活用方法の検討などを行っています。新会員募集中ですので、興味のある方はぜひホームページなどをご覧になってみてください。もちろん私も会員です♪
増毛山道の会(入会案内)
http://www.kosugi-sp.jp/sando/01.html
================
増毛山道の関係者の皆様へ
11月1日(月)に、降雪前に山道の完成度を見る作業がありました。留萌振興局より3名と増毛山道の会より5名参加し、別苅入口より岩尾の終点まで16kmを通して歩きました。天候は曇りから小雨でした。時間は、朝の7時に別苅口を出発し、途中深いところで10cmの降雪がありましたが岩尾到着はちょうど午後3時でした。来年度の一般解放に向けての課題を検討しながら歩きました。看板や歩きにくい個所の整備、橋や階段の設置等もう少し手入れすべき個所をチェックしました。眺めは、暑寒別山塊の暑寒別岳から群別岳、浜益岳、雄冬山の山頂付近はすでに雪景色でした。葉もすっかり落ち、天狗岳の麓標高700mを通るル−トからは、裸の梢越に山の表情が右から左へと少し薄日の差す曇り空の下、変化していきます。右側は頭上に天狗岳の稜線が迫り、岩や笹緑の急斜面が春スキ−の滑降を誘います。
環状林道を越えた辺りより、山道に薄く積もった雪にクマの足跡が続きます。鹿、狐、クマそして我々の足形が出来て行きます。今朝早くの通過でしょうか。岩尾側に降りて行くと子ども連れの親子の足跡。子グマの足跡は紅葉の葉のようで、孫の手にも似て、とても愛らしかったです。これから親子で、来年まで穴の中で命を燃やし続けます。クマの手形を添付いたします。
クマについては、伐採している間は殆ど気配を感じませんでした。秋になり、冬のための捕食活動に入りだす頃から糞等をたまに見ました。入山は複数とベルや笛等の対策をして歩けば、先にクマの方から避けて行きます。道内の山にはどこでも棲息しますので、増毛山塊に限った事ではありません。
それともう一つお知らせいたします。添付ファイルにあります「降りてゆく生き方」上映について、増毛山道の会として協賛いたしましたが、報告が後になりましたことどうかお許しください。来年の2月20日に留萌で上映いたします。映画館で上映せず、地域に受皿が出来れば放映するシステムをとっています。「縄文期の生活に我々の暮らしを戻せ」。「今世紀中に地球温暖化により人類は滅亡する」。そのための小さな一歩を踏み出すきっかけになればと映画は言っています。武田鉄矢主演でアップテンポで進行し、ただ見ているだけでも面白いです。地元での地域起こしの中での出会いでした。
増毛山道の会事務局 拝
(ひろみ) |
どこを開いても、麺・麺・麺…
という麺好きにはたまらない、HOの最新号『麺喰う旅 第1弾』が発売されました。
みなさんご覧になっていただけたでしょうか?
ラーメン、うどん、そば、パスタまで、麺と名のつくメニューが
てんこもりの一冊で
「麺好きってわけじゃない」という方にもお気に入りの一杯が見つかるのでは
と思っています。
「意外な店の評判ラーメン」のコーナーでは、
ラーメン屋じゃないのに、おいしいラーメンを出す店を集めて紹介しています。
取材した「金太の金太」さんは、焼肉屋だけどラーメンも評判。
↑「金太の金太のホルモンはサイコー」という小樽市民は多いはず
というか、ラーメンだけじゃなく全てのメニューが安くて、おいしい店なのです。
焼肉以外のメニューの多くは、13年前のランチタイムオープンに際して、
素早くできてお腹一杯になる料理を、と開発したものだそう。
「専門じゃないからって言って、まずいもの出したくないし、
味にはこだわり持ってやってるからね」と、店主の大坂紀雄さん。
誌面でもラーメンの味噌味は、完成までに3年かかったと書きましたが
その他のメニューも、食べ歩きを繰り返して構想を練り、
何度も試作して作り上げた味ばかりなのです。
特に、ランチ限定「きまり丼」はこの店のランチメニューの代表選手。
ご飯に、炭火焼きした豚バラ肉と目玉焼き、キムチがのったボリュームたっぷりの丼です。
それにしても「きまり丼」って面白いネーミングだなぁと思い、
命名秘話についてうかがってみると
「実はねぇ、この丼のソースの味が決まるまでに1週間もかかってね。やっと味が定まったときに『よし!これで味は決まりだ!』って思ったから、この名前になったんだよね」。
三つの具とご飯に絡んだとき、甘み・塩味・酸味・辛みがバランスよく味わえるソースというのが本当に難しかったそうです。
調合を微妙に変えながら、さまざまなソースを作り、1週間試食しまくったとか。
「ほんと、きつかったよ〜。毎日毎日同じ丼なんだもん」
当時から店を手伝っていらっしゃったお姉さんと顔を見合せて笑いながら、
開発の苦労を話してくれる姿が、なんだか清々しかったです。
早速いただいてみると、本当にバランスがいい。
見た目はかなり脂っこそうに見えますが、
ソースに酸味が利いているうえ、
豚バラは網焼きしてしっかり脂を落としているので脂臭さがないし、
おまけにキムチの辛みが口の中を爽やかにしてくれます。
そして半熟の卵が全体に絡むと甘みとコクも味わわせてくれる…。
最後まで飽きずに食べることができるのです。
いや、これはおいしかった。ほんと。
その上、安いって完璧じゃないですか!
きまり丼は完璧丼だぁ!!
…なんて、紹介にもついつい熱が入ってしまうくらいのおいしさでした。
学生さんや、体が資本の仕事をしている人など
たくさん食べる人の代名詞のようなお客さんが多いというこの店。
「俺も若いころはよく食ったからね〜。たくさん食べる人の気持ちがわかるのよ」
そんな大坂さんが作る料理は、どれもボリュームたっぷりでおまけにコクと旨みが詰まっています。だけど、くどくない。
おまけに食品添加物はほとんど使用していないし、
本当にみんなの味方というお店なのです。
終始笑顔でお話ししてくださった大坂さん。最後に
「来てくれたお客さんが、しっかり飯食って、
昼からも仕事を頑張ってほしいなって思ってるのよ」
と一言。
食べる人への心遣いや愛情が、味にもボリュームにも値段にも込められているんだなぁと、
つくづく感じた取材になりました。
(みさと) |
先日、HO36号で掲載した雄冬についてブログを書いたところ、誌面にお写真を提供してくださった二村高史さんから、こんなメールと追加のお写真をお送りいただきました。
===================================================
(前略)
「ナンバーのない車が走っている」という話は、増毛のユースホステルで聞きました。そもそも雄冬に行こうと思い立ったのは、そこで「ぜひ行くといい」と勧められたからです。波浪注意報がでていたけれど、船は出航しました。沿岸を進むだけなんですが、通常の1.5倍ほど時間がかかったようです。途中の港に泊まった記憶はないので、直接雄冬に行ったのではないかと思います。その日の乗客は、同じユースホステルに泊まった北大生と地元のおばさんと3人だけでした。
雄冬に実際に行ってみると、車にもナンバーが付いていてがっかり(?)。でも、よく見ると、写真のようなナンバーなしの車もあったというわけです。ただ、走っているのを見たわけではなく、車自体もボロボロだったので、単なる廃車なのかもしれません。
民宿に1泊したのち、翌日船で増毛に戻ろうとしたら波が高くて欠航! 宿の人のアドバイスに従って、町外れから道路工事の資材を運ぶトラックに乗せてもらい、これまた増毛のはずれの大別苅というところまでたどり着きました。
-----------------------------------
二村 高史 (FUTAMURA takashi)
http://www.dagashi.org/
なお、お写真に関しては「今回送ったなかには、建設中の国道の写真もあります。また、民宿の前での記念撮影で、一番右に写っている髪ボサボサで、いかにも70年代の学生風なのが当時の私です」とのことです。
ところで二村さんのホームページ「二邑亭駄菓子のよろず話」内のブログにある「スティーブ・ジョブズ『2005年スタンフォード大学卒業式祝辞』」には、本当に感動しました。回り道に見えても無駄なことなんてないのだ、と言えるのかもしれないし、ぼーっとしていたら無駄になりかねないことであっても、どこかで何かの形で生かしていけることは大切な能力なのだ、と言えるのかもしれませんよね。回り道したり、つまずいて転んでばかりの私ですが、めげずに今この時間を大切にしていこうと思います。
二村さん、本当にありがとうございました。
(ひろみ)
※写真提供:二村高史さん(1979年8月撮影)
|
HO 12月号(vol.37)P83で紹介した「Ryu-goow」さんの地図が間違っていました。
大変申し訳ございません。
店の住所は、弊誌に記載されている
札幌市西区琴似1条3丁目3-13 津江ビル2階
で間違いございません。
地図につきましてはお店のHP(http://ryu-goow.com/)にてご確認をお願いします。
読者の皆さま、また関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこと
深くお詫び申し上げます。
(編集部) |
先日、HO35号「チャントヤサイタベテル?」の取材でお世話になった
トマト麺Vegieさん(P107)に、ランチを食べに行ってきました!
取材の時と変わらず、優しい笑顔で迎えてくれた店長の宮下さん。店内BGMはもちろん浅井健一のロックチューンです。
「あれから、HOを見た浅井健一さんのファンの方が店に来てくれたんですよ」
とうれしそうに話してくださいました。
麺を食べ終わったあとのスープに、お待ちかねの「リゾットおむすび」を投入!
カリカリのおむすびに入ったチーズが濃厚なトマトスープに溶けて、あっという間にトマトリゾットに。麺が入っていた時とはまるで別のメニューのよう。ただおむすびを入れただけとは思えません…!
夜は居酒屋になるので、このトマト麺⇔リゾットのように昼と夜とで違った楽しみ方ができるお店です。体もぽかぽか温まるのでこれからの季節にはぴったりですよ。
トマト麺Vegie
札幌市白石区東札幌2条5丁目3-1
村定ビル1階
電話:011・807・4213
さて、先月発売したHO36号「小さな秘境旅」の
秘境神社で拝む(P62-63)で、洞穴の中の太田神社を目指して崖を登る“丸顔新人編集部員”とは…
そうです…私のことです。
たこ焼き、肉まん、おにぎり、まんじゅう、トマトなどなど…
調べ物をしている時に丸っこい食べ物が出てくると、編集長はおもむろに私の方へ寄ってきて
「ほら、これ、友達だぞ」
と、とてもうれしそうにジョーク(本気?)を言って笑わせてくれます。
丸顔話はさておき、太田神社は本当にものすごい場所にあるんです。
長い階段を上り、岩や木やロープにしがみつきながら1〜2時間ほどかけて山を登ります。
「山道を少し歩く」とは聞いていましたが、まさかこんなに本格的な登山をすることになるとは!
しかも、最も恐れていた崖は想像(事前にさんざん脅されていたので、私の中でのイメージはものすごい断崖絶壁に…)よりも怖くないものでした。
確かにかなり危険な場所ではあるのですが、崖の鎖を登っている時間はほんの少しですし鎖自体ロープで固定されている箇所もあったので、グラグラ揺れることなく安心して登ることができます。まんまるの私は転げ落ちたらひとたまりもありませんね…!
山道の入り口には、登山者のマナーについて大きく書かれた立て看板があったのですが、
いざ登り始めてみると心ない登山者の方が投げ捨てたらしいたばこの吸殻を見かけることが何度かありました。悲しいことです。
山の半分くらいまで登った辺りで立ち止まって上を見上げると、
さ…先が全く見えない…!!と一瞬でくじけそうになったためそこからは休まずひたすら無心で登り続けました。
というより、何も考えることができないくらい険しい道のりだったからかもしれません。
長い森をようやく抜け、太陽の光が見えてきた時は本当にうれしかったです!
どんなに辛くても見えない力にそっと背中を押してもらっているような、普段の生活では感じることのできないパワーを太田山の神様からいただけたように思います。
無事に洞穴のなかの祠で手を合わせることができて、お祈りよりも先に感謝の気持ちでいっぱいでした。
そして実は、
この洞窟内で「HOの表紙候補に使えるかも…」と、特別ゲストと秘密の撮影も行われました。
津別町のシゲチャンランドからやってきた(連れてきた?)「ヒョウタン親父」です。
一見、神聖な場所で遊んでいるかのように思われてしまうかもしれませんが、
このヒョウタン親父と太田神社のコラボレーションを実現させようと、小さな撮影会に奮闘していたのです。
結局これらの写真は採用されることなくお蔵入りとなってしまいましたが、
ここで紹介することができて、きっとヒョウタン親父もよろこんでいると思います!
最後に、これから太田神社にトライされる方のため…になるかは分かりませんが、
私の情けない失敗談をいくつかご紹介します。
●虫よけスプレーは、こまめに塗りなおす
→登山前に一度塗ったきりで油断していたら指、脚、背中など20か所以上刺されました
(奴らは服の上からでも容赦なく刺してきます!お祈りしたはずなのに…)
●汗をかいてカラカラに喉が渇いていても飲み物は一気に飲まない
→お腹がタポタポになって、苦しくて登れなくなります。
●登山用の杖を持参する
→登るときはロープに掴まった方が登りやすいのですが、下りは勾配が急なので杖などがあると便利です。(私は杖として使われていたらしいしっかりとした木の棒が偶然山頂に落ちていたので助かりました)
他には帽子、タオル、水、山用の靴、滑り止め付きの軍手があればバッチリです!
女性の方は、流行りの「山ガール」ファッションのようにスカートや短パンの下にタイツ、レギンスという格好よりも、できればズボンで行くことをお薦めします(タイツなどをはいていても虫に刺されるからです!)
今回の取材ではとても貴重な体験をさせてもらいました。地上に戻ってくると、山に登る前よりも気分が前向きになり、「生きているんだ!」というエネルギーが湧いてきます。
拝んでみよう!という方は、雪が降る前に足を運んでみてください。
(みほ)
|
![HO [ほ]](../img/logo.gif)